内科・循環器科

内科は、風邪などのありふれた疾患の診断と治療をおこないます。
当科で十分な診断や治療ができない場合は、適切な専門医をご紹介いたします。
また、健康診断もおこなっております。
健康管理を心がけておられる方や、健康に不安をお持ちの方も気軽にご相談ください。
次に日常よく遭遇する病気を解説を解説しました。
生活習慣病
日本人の三大死因は、1)肺がん・胃がんなどの悪性腫瘍、2)狭心症や心筋梗塞などの虚血性心 疾患、3)脳出血や脳梗塞などの脳血管障害です。
これらは、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活 習慣病があると起こりやすくなります。
自分の意志で行っている生活習慣が原因となって起きる病気であるということです。
脂質異常症
脂質異常症とは、下の 3 つの条件のどれかに当てはまる場合をいいます。
総コレステロール血症 220mg/dl以上
LDLコレステロール 140mg/dl以上
トリグリセリド 150mg/dl以上
血液中のコレステロール濃度が高いと、コレステロールが血管壁にたまります。このたまりを「プラーク」と呼びます。
ストレスなどによる血圧の上昇がきっかけとなり、この「プラーク」を覆う内側の膜が破けることがあります。
するとプラークの中に血液が入りこみ、血の塊ができてあっという間に血管を塞いでしまうと心筋梗塞をおこし ます。
したがって早い時期からコレステロール蓄積を予防することが重要なのです。
治療は、患者さん一人一人の生活様式を把握することからはじめます。その上で、食事療法と運動療法のバランスをとりながら治療を進めます。
食事療法で大切なことは、適正な摂取エネルギーに減らすことです。運動療法としては、早歩き、水泳などの有酸素運動を一日 30 分、週 5 日以上続けることを推奨します。
これでも効果が現れない場合には薬物治療を始めることになります。
動脈硬化の進展を予防するためには、早期に病変を見つけることが重要です。
この動脈硬化の程度を負担なく検査する方法に頚動脈超音波検査があります。脳や心臓の動脈硬化度を推定することができます。
糖尿病
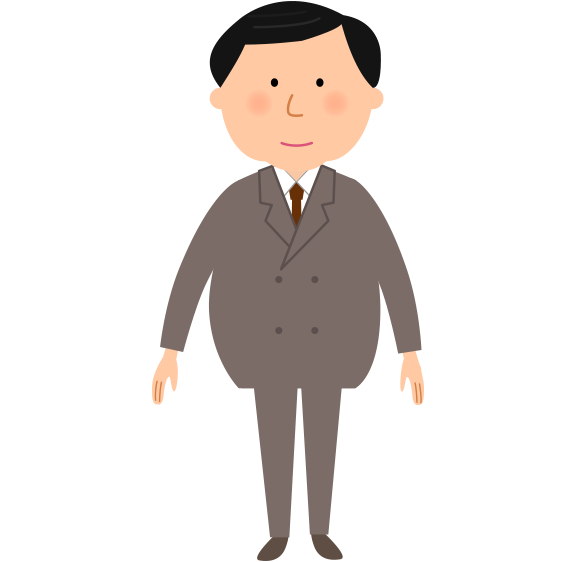
いろいろなくすりが開発され糖尿病の治療に用いられるようになりました。
また血糖を確実に下げるインスリン注射についても「1日以上効果が続くインスリン」が開発されました。
これらを患者さんの「病状」に合わせ て使いわけることによって、血糖を高くならないようにできるようになりました。
しかし、治療の基本は「食事療法と運動療法」であることには変わりありません。
高血圧

健診で高血圧といわれたら、早めに受診してください。
高血圧はまったく症状を自覚することなく、血管をいため、脳、心臓や腎臓などの障害をまねきます。
治療は、食事の塩分を控えることから始めます。一日 6 グラム以下(うめぼし 3 個分)が目標になります。
1週間我慢すれば、ほとんどの方が薄味の食事に慣れ苦にならなくなります。
1)このような食事療法を2ヶ月以上続けてもなお血圧が高い方
2)蛋白尿、眼底動脈硬化や心臓肥大をすでに指摘されている方
3)糖尿病や心臓病をすでに合併している方
以上の方は内服薬による治療が必要になります。血圧が正常になったら、薬の量を減らしたり、やめることも可能です。
自己判断で薬を中断せず、必ず医師と相談することを勧めます。
その他の内科の病気
その他の内科の病気内科は実に様々な病状を診療いたします。「どこか身体の具合がおかしいかも…」そんな時も内科にお越し下さい。
循環器科
心筋梗塞と狭心症
心臓は「心筋」という筋肉でできており、全身に血液を送り出すポンプです。
心筋に酸素や栄養を運ぶ血管は、心臓の外側を這うようにして走っており、冠(かんむり)に似ていることから、「冠状動脈(かんじょうどうみゃく)」と呼ばれます。この冠状動脈が狭くなると、心筋に運べる栄養や酸素の量に限りがきます。この状況で運動すると、心筋は大量の血液を送り出すために大量の酸素が必要となり、酸素の不足が起きます。
このような病気を「狭心症(きょうしんしょう)」といいます。胸(むね)やのど元が、締めつけられる痛みを感じます。運動をやめると数分でなくなります。
さらに冠状動脈が完全に詰まってしまうと「心筋梗塞(しんきんこうそく)」になります。症状は狭心症と同じですが、20分以上持続します。不整脈が起こり突然死することもあります。無事に退院したとしても、心臓の機能が低下し、その後の生活に支障が出てくることがあります。
最近は心臓カテーテル治療といって、足や腕の血管から細い管を入れて、冠状動脈の狭いところや詰まったところを風船やメッシュ状になった金属の筒で広げる治療ができます。
バイパス血管の移植術も行われています。でも、一番いいのはこういった病気にならないことです。
高脂血症、糖尿病、肥満、高血圧、喫煙などの生活習慣病が積み重なると若くても進行します。
不整脈
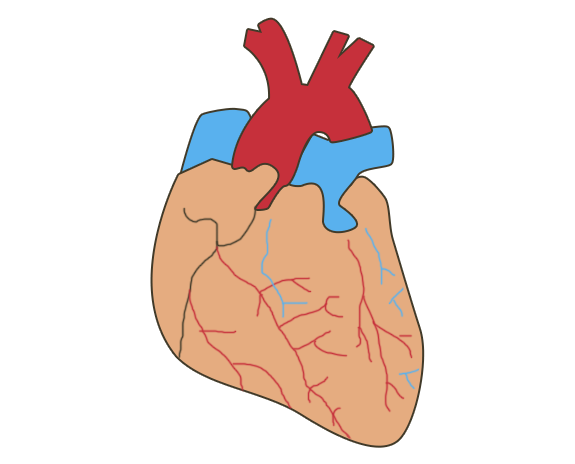
不整脈とは、心臓の脈の異常です。
脈が遅くなる不整脈、速くなる不整脈、両方起こることがある不整脈の3種類にわけられます。
脈が一分間に40 以下に遅くなると、体の姿勢や動作に関係なく「失神(しっしん、気を失うこと)」がおこります。
反対に、脈が速くなると「動悸(どうき)」として感じられます。一分間に150 以上になると、心臓が血液で十分に充満されず、脈が遅い場合と同じように失神がおこります。
【上室性期外収縮】
心臓は心房と心室という血液をためる部屋があります。頭側の心房や心房と心室の間などから起きる脈の乱れのことです。
1週間心電図を記録して診断します。基礎疾患がなく、重症度の低いものについては、治療する必要はありません。
【心室性期外収縮】
心室で起きる脈の乱れです。3回以上連発したり、形がいろいろ変化するものは、突然死につながることがあります。
上記と同様に1週間心電図を記録して診断します。基礎疾患がなく、重症度の低いものについては、治療する必要はありません。
【心房細動】
脈が全く不規則になってしまう不整脈です。
心房細動になると心房の中で血液がよどむため血の塊(血栓)ができやすくなります。
これが心臓から流れ出して脳、小腸、手足などの動脈を詰まらせると重大な病気を起こします。
これを予防するため、血栓をできにくくする薬を内服することをお勧めします。
【房室ブロック】
心房と心室の間には、電気的な流れを伝える電線があるのですが、この流れが悪くなってしまうのが房室ブロックです。
失神を伴う場合は、ペースメーカー移植術が必要となります。
【洞不全症候群】
心臓は自動的に動いていますが、そのための規則的な刺激を作っているのが洞結節というところで、心臓の頭側にあります。
この洞結節の機能が低下して脈が非常に遅くなります。失神を伴う場合は、ペースメーカー移植術が必要となります。
不整脈以外の心電図異常
不整脈以外の心電図の異常にも、いろいろな種類があります。その中でも多いものが、左室肥大、ST、T波の異常です。
【左室肥大】
高血圧が続くと、心臓に負担がかかり、筋肉が厚くなってきます。これを「肥大(ひだい)」といいます。
肥大は収縮力の低下をおこします。壁が厚くなるが全体が大きくならない「求心性左室肥大」と、壁が厚くならず全体が大きくなるする「拡張性肥大」の2つのタイプに分けられます。心エコーにより診断します。
【ST、T波異常】
心電図の最も大きな波のうち、後半の部分をST部分、T波といいます。
ST 部分が上昇あるいは低下していたり、T波が低かったり、ひっくり返っていたりする所見は、原因となる疾患がない場合のほうが多いです。
ですが、1週間心電図記録や心エコーなどを実施して、原因となる疾患が隠れてないことを確認する必要があります。
大動脈瘤
「大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)」とは、太い血管が動脈硬化のために弱くなり、血圧に耐え切れず膨らんでこぶのようになったものです。
風船と同じように、大きくなると破裂しやすくなります。
いったん破裂すれば、痛みとともに出血して、生命が危うくなります。
胸部にて6cm、腹部にて 5cm を超えるものは手術が勧められます。胸や腹部を切開して人工血管を埋め込みますが、高齢な方やがんの治療中の方は、脚の付け根から動脈内部を通じて大動脈瘤の内側に人工血管を挿入する方法が選ばれます。
「解離性(かいりせい)大動脈瘤」という病気もあります。
大動脈の壁の内側に裂け目が入り、ここから血液が入り込んで内側の壁と外側の壁の間が裂けてゆく病気です。破裂をまぬがれて、数ヶ月経過すると太くなってくるため解離性大動脈瘤と呼ばれていましたが、最近は「急性大動脈解離」と呼ぶようになりました。
心臓に近い部分の大動脈解離は三日以内に破裂することが多く、緊急手術が不可欠となります。
これらの病気を防ぐためには、高脂血症、糖尿病、肥満、高血圧、タバコなどの危険因子をいかに少なくして生活するかにかかっているのです。
慢性動脈閉塞症
慢性動脈閉塞症とは、手や足に血液を送っている血管の内腔が狭くなる病気をいいます。
心臓から手や足の指に至る途中で狭くなると、その先の筋肉に十分な血液がいかなくなります。
このため、一定の距離を歩くと、きまってふくらはぎやふとももが痛くなる「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」がおきます。
さらに進行すると、皮膚にも血液がいかなくなり、激しい痛みとともに、手や足が黒くなる「壊疽(えそ))の状態となり、切断しなければならなくなります。
喫煙者では、禁煙が治療の第一歩となります。そのうえで、抗血小板薬を内服していだだきます。
側副血行を促進する歩行などの運動療法も追加します。
以上の治療を 3 ヶ月間実施しても症状が改善しない場合は、カテーテル拡張術やバイパス移植術などが必要となります。
脳梗塞
脳梗塞(のうこうそく)は、脳に血液を送っている血管が動脈硬化により詰まって起きる病気です。
5分位から数時間にわたって、左右いずれかの手足に力が入らない、ろれつが回らない、などの症状がでることがあります。
いったんは症状がなくなりますが、数日以内に血の固まり(血栓)により完全に詰まり脳梗塞になることが多いことが知られています。
したがって、このような症状がでたら、すみやかに医師の診察を受けてください。
アスピリンなどの血栓ができにくくする薬を内服することにより、脳梗塞の発症をかなり防ぐことができます。
健康診断のすすめ
30 歳以上になったら、少なくとも年に一度は、からだの具合を診断していただいたらいかがでしょうか。
健康診断は、生活習慣病の予防対策の一環として、市町村や事業所の健康保険組合が実施しています。
もちろん当院でも受け付けておりますので、ご相談下さい。
健診の種類
一般健診、成人病健診、がん検診などがあります。

